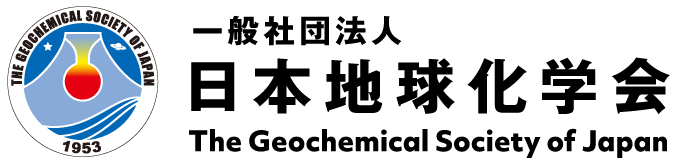日本地球化学会会員の皆様
地球化学会法人化タスクフォースよりお知らせ致します.
日本地球化学会法人化に向けた準備作業を進めております.
法人化の意義や検討の現況について,Q & A 形式にまとめましたので,お読みいただければと思います.
昨年9月の総会で法人化準備作業の開始およびそのための予算が承認されました.その後,法人化タスクフォース(圦本会長,川幡副会長,平田副会長,鍵GJ編集長,中川会計幹事,橘庶務幹事)が立ち上がり,2月の幹事会,評議員会を経て,最速で 2017年内の移行が可能なスケジュールで検討することになり,準備を進めています.法人化への最終判断は本年 9月の年会において開催の総会で会員の皆様にしていただきます.
6月に開催の今年度第二回目の評議員会の後,検討中の法人の定款案,規程案についても皆さんにご覧いただけるように致します.
今後も情報を公開していきますので,ご質問などありましたら,庶務幹事(affairs@geochem.jp)までご連絡ください.Q & A をアップデートする形でお答えしていきます.今後も更新していきますので,本ページでご確認ください.
2017年5月30日
日本地球化学会法人化 Q & A
Q. なぜ法人化するのですか?
A. 法人化する学会が昨今増えていますが,その背景には社会からの要請や日本学術会議から法人化を推奨されていることなどがあります.本会のように任意団体でも,会費収入や学会誌,年会の事業費が課税対象となる場合があり,最悪の場合,脱税行為として認められる危険があるためです.日本学術会議は2013年3月に報告した「新公益法人法への対応及び学協会の機能強化のための学術団体調査結果」の附記文書として,法人格を取得していない学会に対して,可及的速やかに法人格を取得することを勧めています.こうした状況を踏まえ,本会も他学会の動向を参考にしながら,以下に述べるメリット・デメリットの検討をおこない,法人への移行準備を始める判断を致しました.移行準備を進めることについては,2016年9月の総会で承認されています.
Q. 法人化のメリットはなんですか?
A. 1. 学会としての社会的認知度や信用度が高まります.政府・自治体などの公的機関からの研究受託や助成などを受けやすくなります(現在は任意団体のままでも助成を受けることができていますが,将来にわたり可能である保証はありません).本会が今後もゴールドシュミット会議の運営に主体的に協力し,日本国内での開催を検討していく上でも確固たる社会的ステータスをもつことは重要となります.また,地球環境問題などに対し,本会が社会に向けて情報や意見を発信していく機会や責任が益々増えることが予想されますが,情報を発信する場合にも,信用度の高い情報として受け取られるようになります.
A. 2. 学会名で契約,雇用,売買,貸借などの法律行為が可能となります.これまでは銀行口座の開設や諸契約を会長などの個人名義でおこなってきました.法人化することにより,学会の名義で資産を持つことが可能となり,私法上の取引主体としての地位も確保されます.学会がおこなう行為や構成員の責任・義務などが法的に明確となった状態で運営することも可能になります.また,公益法人会計基準に準拠して,会計処理をおこなうことで税務の扱いが明確化され,透明性の高い会計処理をおこなうことができるようになります.
Q. 法人化のデメリットは何ですか?
A. 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般法人法)の定めに従った運営をすることになり,運営事務が少々煩雑になること,法律の規制が多くなることが挙げられます.そのため,会計業務の委託も検討していますが,学会の運営業務を大きく変更する必要がないことは確認できています.会員の権利・義務や会費の変更もありません.事務処理の煩雑化はデメリットではありますが,これによりしっかりとした学会運営が可能になります.
Q. 本会が移行を検討している「一般社団法人」とはどのような法人ですか?
A. 一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般法人法)に基づいて設立された社団法人のことです.「社団」とは人の集まりを指し(「財団」は財産の集まりを指します),それに法律上の人格(法人格)を与えたものを社団法人とよびます.本会は収益事業で発生する剰余金の分配をおこなわない(営利活動をおこなわない)非営利型の一般社団法人の設立を検討しています.収益事業のみが法人税の課税対象となり,それ以外は非課税となります.一般社団法人は登記のみの簡単な手続きで設立することができ,最低限必要な機関(社員総会,理事会など)の設置,管理に関する事項が法律で規定される以外は,事業や運営に対して,行政の監督も受けません.そのため,学会のような学術団体の法人化に向く制度として広く利用されています.一般社団法人を経て,公益社団法人(公益事業を主に目的とする法人)に移行することも可能です.学術活動は公共の利益となるものであり,公益社団法人となることで社会的信用度はさらに高まります.しかし,事務作業の負担は相当大きく,行政による監督も受けることになり,本会の運営規模には適さないと判断されます.したがって,現状は公益社団法人への移行は考えていません.
Q. 法人化によって変わること・変わらないことを具体的に挙げると何ですか?
A. 1. 法人化で変わること
- これまで秋の年会でおこなってきた「総会」が「定時社員総会」となります.社員総会は一般社団法人の「意思決定機関」です.一般社団法人は原則として,事業年度終了後から3カ月以内に税務申告が必要になります.税務申告のためには,定時社員総会で決算の承認を得る必要があります.本会はこれまで9月の年会時に総会を開催してきました.これまでどおり,秋の年会での総会開催をおこなうため,事業年度を現在の「1月1日-12月31日」から「8月1日-7月31日」と変更することを検討しています.
- 本会の運営に関する具体的決定は「評議員会」がおこなってきましたが,名称が「理事会」と変わります.理事はこれまでの評議員同様,会員による選挙で選ばれます.
- 会長,副会長は一般法人法上の「代表理事」となります.代表理事は理事会で選出されます.会員による直接選挙で選ばれることはありません.しかし,これまでのように会員の意志の反映が可能となるように,理事選挙にあわせて,会長,副会長候補者に対する意向投票をおこなう予定です.
- 法人化に伴い,一般法人法に則って作成する会計書類が増えるなど,会計業務の負担が増大することが予想されます.そのため,国際文献社への会計業務の委託の可能性を検討しています.
A. 2. 法人化で変わらないこと
会員の権利,会費,年会,学会誌などほとんどのことは現在と変わりません.一般法人法に則った運営をおこなうために,事務業務の変更などはありますが,目に見える学会運営は,上に述べた事業年度変更以外には,現在の形態と大きく変えずに移行できるように検討を進めています.
Q. 法人化の準備はどのように進んでいますか?A.
- 2016年9月の総会で法人移行準備活動の開始,およびそのための予算を承認いただきましたので,2016年10月に法人化タスクフォース(TF)を立ち上げました(メンバー:圦本会長,川幡副会長,平田副会長,鍵GJ編集長,中川会計幹事,橘庶務幹事).
- 2017年1月に公認会計士事務所をTFメンバーが訪問し,本会の法人化に関して,特に定款策定,スケジュール,手続きについての相談をおこないました(「定款」とは社団法人の目的,組織,業務などを定めた根本規則のことです).訪問した公認会計士事務所は,これまでに多くの学会の法人化の支援業務をおこなっており,地球惑星科学分野の学会の法人化も最近担当された事務所です.本会が業務委託している国際文献社とも連携をしています.
- 1月の公認会計士事務所での相談に基づいて作成した定款第一案,スケジュール,手続きなどに関し, 2017年2月に開催した幹事会,評議員会において,TFメンバーからの説明ののち,議論をおこないました.評議員会において,最短で2017年内に新法人への移行が可能なスケジュールで進めることとし,法人化準備予算で公認会計士事務所と契約を結ぶことが承認されました.
- 2017年3月,TFメンバーが公認会計士事務所を訪問し,評議員会での議論を基に,定款案の細部の調整をおこないました.調整した定款案は,評議員会に展開され,メールにて議論が進められています.本会の現行の各規定を新法人の規定へと移行する作業も,公認会計士事務所とTFメンバーで進めています.5-6月におこなうメール評議員会で定款案の議論を再度おこなった後,会員の皆様に定款案をご覧いただき,ご意見を頂戴するようにいたします.いただいたご意見やご質問への回答を学会ウェブサイトでQ&A形式でお答えしていきます.
- 2017年9月の総会で,法人化をお認めいただけるかどうかの議論をおこない,承認された場合には2017年内に新法人へと移行します.その場合,今回の選挙で選ばれる評議員は新法人の理事となり,選挙で選ばれる会長,副会長は新法人の代表理事候補者となります.
Q. 法人への移行期の年会費はどう扱われますか?
A. 9月の総会で法人化が承認され,2017年度内に法人化する場合,法人の初年度分会費請求をこれまでの本会の会費請求と同じく,2017年12月におこなう予定です.会員の皆様からは現在の任意団体の年会費として,2017年12月までの会費を支払っていただいており,また,法人の会計年度最終日は7月31日となるため,初年度年会費は2018年1月からの7月までの7ヶ月分とし,正会員の皆様には6000円,シニア会員および学生会員の皆様には3000円,賛助会員の皆様には12,000円/口の会費請求をさせていただきたいと思います.その後,法人第二年度の会費を2018年7月に通常の会費額で請求させていただきます.会計年度変更に伴い,2017年,2018年は会費請求時期や請求額がわかりづらくなるかもしれませんが,会員の皆様には不利はありませんので,ご了承ください.なお,年度内法人化の場合,本年7月1日以降,法人化までの期間に入会された会員の皆様につきましては,年末の初年度請求(7ヶ月分)をおこないません.また,現在,学生パックの学生会員の皆様についても,初年度請求はおこなわない予定です.
Q. 法人の会計業務委託とはどのようなものでしょうか?
A. 法人化後,学会運営は一般法人法に則っておこなう必要があり,会計業務の負担が増大します.そのため,法人化TFでは国際文献社へ会計業務委託の可能性を検討してきました.検討のなかで,出金業務含めすべて委託する場合,出金業務はこれまでどおり会計幹事がおこない,決算書作成などの新たに生じる業務のみを委託する場合などの様々な委託形態を議論してきました.結果として,会計業務すべてを委託した場合も,学会運営には支障がないという結論に達しました.法人の会計業務をすべて委託するという案に関して,幹事会での議論の後,6月の評議員会に提案し,審議の後,承認されました.これにより,法人化された場合の会計業務はまず完全委託で始めることになります.ただし,法人としての運営を進めるなかで,学会側で対応可能であると判断された項目については適宜,委託ではなく学会の業務としていく方針で進めます.なお,完全委託とする場合も,年会の会計業務,科研費(国際情報発信強化)の会計業務についてはそれぞれ,これまでどおり年会LOC,GJ編集委員長がおこなう方針でおります.